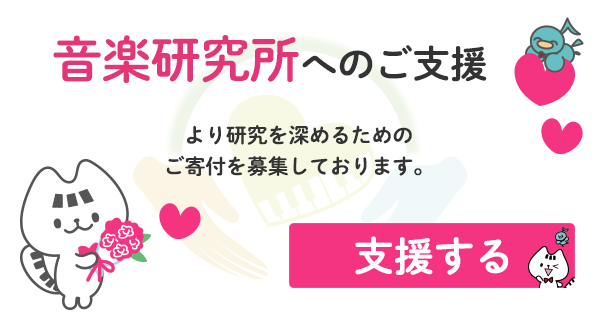ピティナ音楽研究所 2024年度研究経過報告会レポート
発足3年目を迎えたピティナ音楽研究所(PRIM)は、2025年3月20日(木・祝)に東音ホールで2024年度研究経過報告会を開催しました。音楽学・音楽教育学・社会学・情報学と広い分野にわたる発表が行われ、5名の所属研究員がそれぞれの専門領域における成果を披露。オンラインも含め多くの参加者を集め、活発な質疑応答が交わされる充実した報告会となりました。
研究経過報告会 レポート
報告会は、研究所事務局による2024年度の概況報告から始まり、続いて福田氏(専務理事・専門研究員)による報告、その後に各研究員が成果の報告を行いました。
参加者からは、学際的で多様な視点からの研究報告を一度に聞くことができ勉強になったという感想や、個別の発表についてのコメントも集まりました。

上田泰史

パリ音楽院ピアノ教授ジョゼフ・ヅィメルマン(1785~1853)研究――モノグラフィ出版に向けた進捗状況
上田氏はソルボンヌ大学で執筆された博士論文を基にした研究について発表。19世紀前半のパリ音楽院ピアノ教授ジョゼフ・ヅィメルマンに関する初の研究成果として、新たな資料に基づき加筆・推敲を進めてきたモノグラフの構成を紹介しました。この10年余りの間、新たに見出された様々な資料を基に論文を加筆・推敲し、フランス国立科学研究センター(CNRS)の名誉研究ディレクターであるフロランス・ジェトロー氏、およびソルボンヌ大学教授ジャン=ピエール・バルトリ氏の助言を受けつつ、原稿の編集を続けてきたとのことです。今年度は草稿の仕上げを目指し、フランス語の本文と付録を整理。発表では、全14章からなる草稿の構成を示し、ヅィメルマンがパリ楽壇で果たした多面的な役割(ピアニスト、作曲家、教育者、社交人、芸術家相互扶助活動)を紹介し、彼の19世紀ピアノ音楽文化における意義を明らかにしました。
中村栄太

自動採譜と楽譜-MIDIアライメントを用いたピアノ演奏誤り解析手法に関する研究
昨年12月に着任した中村氏は、約3ヶ月間の研究活動の報告として、「自動採譜と楽譜-MIDIアライメントを用いたピアノ演奏誤り解析手法に関する研究」の概要を発表しました。この研究では、グランドピアノ、アップライトピアノ、電子ピアノなど多様な楽器や演奏環境で使用可能な自動MIDI採譜手法の開発を目指しています。また、楽譜情報とMIDI情報をアライメントさせることで、演奏された音と楽譜上の音とのずれを検出し、演奏の誤りを解析する手法についても研究しています。情報学分野の専門家として、研究所内の様々な技術的課題に対するサポートも行っていることが述べられました。
菅沼起一

チェルニーの即興演奏教本における伝統と現代の実践への応用
菅沼氏はディミニューションと呼ばれる即興的な装飾技法の分析を専門としており、同時にリコーダー奏者としても活動しています。その知見を活かして、エチュードの作曲家として広く知られているカール・チェルニーの即興演奏の教本を分析する研究について発表しました。発表では、チェルニーの『ピアノで弾くファンタジーへの体系的手引き』を取り上げ、彼の即興メソッドに見られる「前時代からの伝統」を考察。具体的には、教育メソッドにおけるイタリアのディミニューション教本からの影響、エチュードとの関連性(エチュードの練習が即興演奏の基礎となること)、小節線のない楽譜による前奏曲の存在(バロック時代のプレリュードの伝統)、そして自然模倣説との関連が示唆される点について解説しました。
加えて、特に既存の楽曲の前に演奏する前奏曲に焦点を当て、それらを現代のピアノ演奏・教育実践に応用する可能性について、実際の演奏デモンストレーションを交えながら検討。チェルニーの即興教本で示された譜例とベートーヴェンのピアノソナタなどを組み合わせた演奏例を紹介し、即興演奏の導入の可能性を示唆しました。
松川亜矢

音楽大学の機能:学生のディスポジション形成と「教員-学生」関係に着目して
松川氏は、音楽の高等教育機関(音楽大学)が現代日本において教育的、社会的にいかなる機能をもつかを検討するため、今年度主に卒業生、現役学生および現役教員へのインタビュー調査をおこなった研究について発表しました。松川氏は教育社会学と高等教育論のアプローチで音楽大学を研究しており、インタビューを通して、学生の職業音楽家としてのディスポジション(人々の行為や実践を方向づける、個人の内面化された性質)の形成・変容過程と、そこに作用する「教員-学生」関係の重要性を明らかにしたと述べました。
発表では、こうした研究活動を通して得られた知見について報告し、今後の展望について述べました。特に、音楽大学卒業後に個人教師となる女性のキャリアプロセスに着目した研究や、現役学生と教員の関係性についての調査結果を紹介しました。
福田成康

活動報告(ISMIRでの発表、および国立情報学研究所でのデータセット公開計画)
福田氏は、ピティナ音楽研究所の研究員としての活動報告として、まず自身がGoogle ScholarのTop Publicationsで1位ランクのISMIR(国際音楽情報検索学会)で論文を発表した様子を報告しました。サンフランシスコで開催された学会での発表内容や、国際的な研究動向について触れました。次に、国立情報学研究所の情報学研究データリポジトリでデータセットを公開する計画を紹介。ピティナが長年にわたり蓄積してきた豊富なデータを提供することで、ピアノ音楽研究の発展に貢献したいという意向を示しました。このデータセットは、他では見られない貴重な情報を含むとして、国立情報学研究所からも高い関心が寄せられているとのことです。
質疑応答・閉会
各発表後には、会場参加者およびZoom参加者からの質問に対して、発表者がそれぞれ回答する質疑応答の時間が設けられました。活発な意見交換が行われ、研究内容についてさらに深い理解を得る機会となりました。
すべての発表終了後、研究所所長より閉会の挨拶があり、盛況のうちに2024年度研究成果発表会は幕を閉じました。
※来年度の研究計画や今後の研究所の活動については、随時ピティナ音楽研究所のウェブサイトやSNS等でお知らせいたします。今後ともピティナ音楽研究所の活動にご注目ください。
ピティナ音楽研究所について
2022年4月に発足したピティナ音楽研究所(PRIM)は、上級研究員1名、研究員1名、協力研究員2名、専門研究員1名の計5名の研究員が所属し、音楽と音楽教育に関わる様々なテーマについて研究を行っています。一般社団法人全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)定款の第42条を設立の根拠として、同協会の本部事務局、専門委員会とならぶ機関として設置されています。