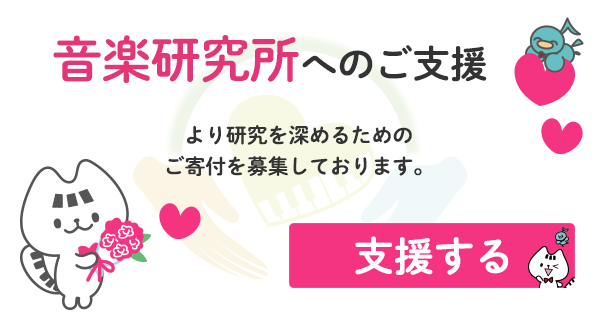研究レポート: ラウンドテーブル「友愛と歓待:歴史都市における共生の射程」に参加して(4/4) 上田泰史
- サントリー研究助成2024年度共同研究「「歓待インフラストラクチャー」から読み解く近世ヨーロッパ都市文化=空間構造の比較研究」(研究代表者:坂野正則)
- 都市史学会ワーキング・グループ「都市における文化=空間構造から捉える全体史」(文化=空間構造論WG)
登壇者による鼎談では、坂野先生がいくつかの論点について登壇者に意見を求めた後、司会を京都工芸繊維大学の赤松加寿江先生(ご専門はイタリア近世都市史)に引き継ぎ、議論がフロアに開かれました。音楽にゆかりが深くピアノも演奏される赤松先生は、このイベントでピアノ奏者の平井千絵先生と13年ぶりに再会を果たしました。平井先生は、東京藝術大学古楽科の大学院の非常勤講師として、フォルテピアノを教えられています(2025年9月現在)。
マイクを手にした平井先生は、フォルテピアノ特有の音響と空間の関係と、オランダ留学時代に体験された互助精神の重要性について語られました。
 (提供:坂野正則)
(提供:坂野正則)
以前、私は赤松先生の鎌倉のサロンで演奏したいと思いお声がけしたとき、お客様と肉声が伝わるくらいの距離感で演奏し、その後にコミュニケーシションをとりたいと思いました。楽器の手触り、音色、指の感触――フォルテピアノはモダンピアノよりも鍵盤がはるかに軽くて浅いんです。操ったときの感覚も違うし、音もモダンピアノよりずっと小さい。この違いを意識したのは、日本でピアノを学んだのち、14年間にわたり修行をしたオランダでのことでした(平井先生は2012年に帰国)。フォルテピアノで演奏するということは、楽器を弾くことだけを考えればよいというわけではありません。オランダでフォルテピアノ演奏していたとき、普段の会場は肉声で会話できる程度の空間でした。丁度この(鳩山会館の)大広間くらい。そのような場所は、現代のピアノでは音が大きすぎるんです。フォルテピアノはうるさくないどころか、現代の耳にはちょっと物足りないと感じられるくらい。だけれど、一定の時間演奏する間に聴き手の耳は慣れ、弱音は内面の中におりていき、お客様さんは自分の心の奥と向き合う時間を過ごすことになる。ですから、演奏後、お客さんは普通の音量で話すことも憚られるくらい、感覚が研ぎ澄まされる経験をします。演奏会の後にワインやお菓子を出してお客さんとコミュニケーションをとりたいと思うのは、その音楽的余韻から感覚を現実に戻すためなんです。
けれど、日本の演奏会場では、そうした演奏後の活動についてはなかなか許可がおりなかったり、開館時間にリミットがあったり、追加料金があったりと、容易ではありません。
ところで、私は1年半前に佐久市に移住したのですが、そこにはもっと自由な考えの方々と出会いました。佐久市には面白い慣行があって、生活改善方式というのですが、冠婚葬祭の負担を減らすために、質素に行うことや、お返しを少額にすることを決めた申し合わせがあるんです。お互いに生活を気遣えるということで思い出されるのは、留学時代の経験です。オランダは古楽復興の先駆的な国で、一度廃れたチェンバロなど古楽器による演奏を現代に蘇らせる運動を推進してきました。あるとき、私が事故に遭い、私の師匠であるスタンリー・ホッホランド先生に代役を頼んだことがありました。コンサート後、先生はその演奏会の収入を丸ごと私に手渡してくれた。先生のお仕事に対する謝礼なのになぜ私に渡すのか、と問いかけると、先生は、あなたはフリーランスの音楽家で保障がないのだから、と生活を気遣ってくださったのです。オランダ古楽器奏者の互助精神、そして富を独り占めしない先生のような考え方が芸術家の生活を支えるインフラになっていたことを思い出しました。
平井先生のお話は心温まると同時に、歓待や友愛という切り口から音楽活動の再考を促すものでした。とくに演奏という営みを楽器・演奏・空間・聴き手とのコミュニケーションの総体として捉える視点が印象的です。音楽には演奏の場において奏者と聴き手とを、言葉を用いずに近接させる力があります。この力は、音楽を取り巻く社交を通した共同体意識を通して、人と人のつながりを強くします。
現代のコンサート形式を振り返ってみると、コンサート会場は非日常的で特殊な空間です。演奏中は咳をするのも憚られ、聴き手は全員が静寂の中で演奏に耳を傾けます。演奏会空間が非日常的な場として特権化されたのは、19世紀に近代的なコンサートホールが世界各地の都市に作られ、「天才的」とされる作曲家の音楽に全身全霊を傾けて聴取するという習慣が確立されてからのことです。そこでは、防音システムにより、ホール内の世界は外界とは隔絶され、演奏が非日常的な体験として享受されるよう設計されています。この場合、ホールの「内」と「外」を結ぶ空間と時間が存在しないため、ひとたび扉の敷居をまたいで外にでると、唐突に日常世界へと連れ戻される気がします。
だからこそ、現代ではこの日常性と非日常性をゆるやかに結ぶ時間と空間に関心が集まっているのではないでしょうか。今日では、練習を公開したり、演奏会に先立って対面式の勉強会を開催するなど、聴き手と演奏家のコミュニケーションを図りながら、演奏会の非日常性と日常性の間をとりもつための様々な工夫が講じられています。
平井先生が求める演奏後の歓待空間とは、フォルテピアノの音量や繊細な音色が作り出す非日常から、奏者や聴き手を日常へと穏やかに移行させてくれるような「あいだ」の時間と空間だと言えます。
こうした「あいだ」の時間・空間は、奏者と聴き手が「同じ時空を生きている」という実感を、言葉を介さずに強めてくれます。それは、イギリスの音楽学者ニコラス・クックがオーストリアの社会学者アルフレート・シュッツの言葉を借りて言うように、「同じ流れを通じて生を共有し、ともに老いる」※注釈1音楽的時間の喜びを互いに確かめ合い、眼の前の人との関係をゆっくりと強化する時間と空間なのです。
現代は、スマホやパソコンで簡単に音楽を聴くことができる時代です。少しお金を出せば、海外の著名な音楽家のコンサートにも足を運べます。しかし、そのような時代だからこそ、こうした利便性の裏返しとして、聴き手や演奏者、企画者が互いに語らい、音楽を通していまを共に生きているという実感を取り戻したいという根源的な欲望が顕在化しているのかもしれません。
日常と音楽的時間が作り出す非日常の「あいだ」の時間と空間を入念に設計し、演奏者と聴き手の新たな繋がりを紡ぐことーーこれを可能にするのが「歓待」の空間としての演奏会のあり方であり、コンサートホールの中で忘れかけている音楽を通した「共生」の実感を、私たちに再びもたらしてくれるのではないでしょうか。
- ニコラス・クック『音楽とはーーニコラス・クックが語る5つの視点』福中冬子訳、東京:音楽之友社、23頁。
京都大学大学院人間・環境学研究科准教授。ピティナ音楽研究所 上級研究員、ピティナ・ピアノ曲事典共同編集長。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学修士課程修了後、パリ国立音楽院ピアノ科における教育(1841〜1889)についての研究で博士号を取得。パリ第4大学で19世紀フランスのピアノ教授P.J.G. ヅィメルマンに関する研究で同大学で博士号を取得(満場一致)。2015年、日本学術振興会より育志賞を受ける。著書に『「チェルニー30番の秘密」ーー練習曲は進化する』(春秋社、2017年)、『パリのサロンと音楽家たちーー19世紀のサロンへの招待』(カワイ出版、2018年)。日本音楽学会、地中海学会会員、フランス音楽研究所(IReMus)在外通信員、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会評議員。