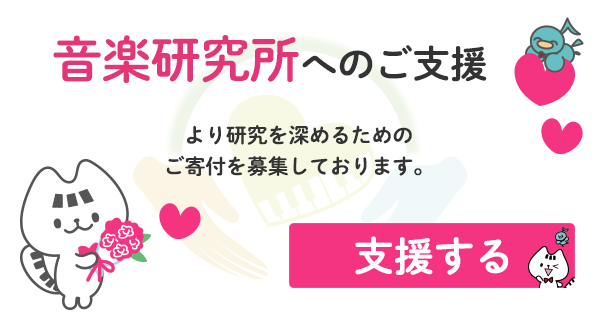研究レポート: ラウンドテーブル「友愛と歓待:歴史都市における共生の射程」に参加して(2/4) 上田泰史
- サントリー研究助成2024年度共同研究「「歓待インフラストラクチャー」から読み解く近世ヨーロッパ都市文化=空間構造の比較研究」(研究代表者:坂野正則)
- 都市史学会ワーキング・グループ「都市における文化=空間構造から捉える全体史」(文化=空間構造論WG)
- 2024年12月22日の午後、東京都文京区音羽に位置する鳩山会館で「歓待インフラストラクチャー」研究東京ラウンドテーブル「友愛と歓待:歴史都市における共生の射程」が開催されました。本記事は、そのレポート(第2回)です。第1回の記事はこちらから
13時過ぎ、坂野正則先生による趣旨説明でラウンドテーブルは幕を開けました。まずは「友愛と歓待」というテーマを通して歴史都市と共生について考えるために、3つの論点が提示されました。
- 友愛とは何か:フランス語のfraternité/英語のfraternity(兄弟愛)に対応するもので、友愛を形作るつながりや、それから排除されるものについての議論
- 友愛を実現するための空間:友愛を支える装置としてのインフラとしての歓待空間の役割についての議論
- 歴史都市における共生:友愛という理念と都市社会の関係・異なる都市間の比較の可能性についての議論
その上で、「友愛」という大きな主題について、歴史的な説明がなされました。以下に、その説明を要約します。友愛とは、社会を構成する人々の理念・価値観・規範・趣味・目標・道徳・嗜好によって関係が築かれることによって生まれる関係です。今日、日本語で友愛という場合、その直接的な使用は中世キリスト教世界に求められます。そこでは、血縁的な上下関係に基づかない、水平的な社会集団を形成する役割を果たしました。但し、あくまでキリスト教信仰内部での友愛ですから、異教徒は除外されます。「友愛」の理念は、さらに古代ギリシアにまで遡ります。
友愛に相当する「フラトリア」は、都市(ポリス)と家(オイコス)を結ぶ中間的な社会集団で、フラトリアの構成員と認められることが市民であることの前提でした。逆に言えば、市民の一員であれば、家の財産が保証されました。
一方、ヨーロッパ近代市民社会においては、職人組合であるギルドなどの功利集団とは異なる、非功利の友愛団体が成立します。フリーメイソンがその代表格で、会員を結びつけるのは、会員だけが共有する「秘技」の伝授でした。
こうした友愛的関係を支えたのは都市で発達した歓待という営みであり、洋の東西を問わず、さまざまな傾向をもつ社交集団を成り立たせてきたのです。
 登壇者による鼎談にてマイクを持つ坂野先生(提供:坂野正則)
登壇者による鼎談にてマイクを持つ坂野先生(提供:坂野正則) 登壇者は、私を含め次の3名でした(発表順)。
田瀬望先生(武蔵大学):フリーメイソンの成立と友愛理念の様々な実践実態についてご発表されました。
上田泰史(筆者):19世紀フランスの音楽サロンについて紹介しました。
谷直樹先生(大阪市立大学名誉教授):近世都市(京都・奈良・大阪)の町会所の機能・空間についてご発表されました。
このリポートはピティナで公開するものですから、音楽の話題を提供した筆者の発表について要約を、次回の記事で提示することにします。
次回、第3回の記事はこちらから
 会場写真 2階大広間へ(撮影:筆者)
会場写真 2階大広間へ(撮影:筆者) 京都大学大学院人間・環境学研究科准教授。ピティナ音楽研究所 上級研究員、ピティナ・ピアノ曲事典共同編集長。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学修士課程修了後、パリ国立音楽院ピアノ科における教育(1841〜1889)についての研究で博士号を取得。パリ第4大学で19世紀フランスのピアノ教授P.J.G. ヅィメルマンに関する研究で同大学で博士号を取得(満場一致)。2015年、日本学術振興会より育志賞を受ける。著書に『「チェルニー30番の秘密」ーー練習曲は進化する』(春秋社、2017年)、『パリのサロンと音楽家たちーー19世紀のサロンへの招待』(カワイ出版、2018年)。日本音楽学会、地中海学会会員、フランス音楽研究所(IReMus)在外通信員、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会評議員。