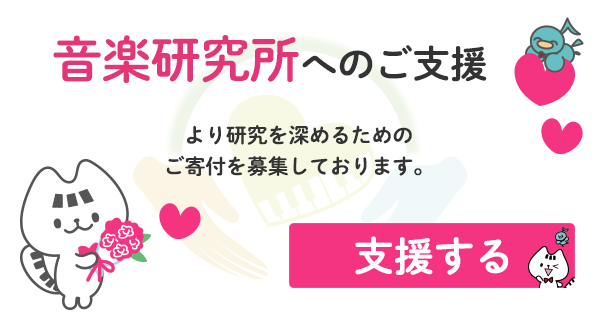チェルニーに学ぶ!第5回『即興に必要な学びとは?』(Op. 200②)
~創造の楽しさを日々の練習に~
みなさま。こんにちは。
第四回に引き続き、今回もチェルニーのピアノ教則本『ピアノで弾くファンタジーへの体系的手引き Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte Op.200』(n.d. [1829])の序論を見てゆきたいと思います。前回は序論の前半を取り上げました。今回は後半、序論の残りを取り上げます。では、早速続きに参りましょう。
作曲することと同様、即興する、ということには次のものが備わっている[べきである]。
第一:天賦の才。これは、ほとんどの場合幼少期にはすでに明らかになっており、創造性、活き活きとした想像力、豊かな音楽の記憶力、機転の効く思考力、恵まれた良い形の指などが含まれる。
第二:あらゆる種類の和声の基礎的な教育。それにより、適切な転調における敏捷性は、すでに演奏者にとっての天性となっていることだろう。
第三:そして、十分に鍛えられた演奏技術(ヴィルトゥオジティ Virtuosität)。こうして、あらゆる難易度、あらゆる調性で、そして美しく、心地よく、優雅な演奏に関わるすべてのことにおいて、指を最高に巧みに使うことができる。想像力が最高の楽句を与えても、指先がそれを芸術的な能力と確実性をもって実行できなければ、それは無駄でしかないからだ。
ところで、公開の場で芸術的な即興演奏に専念しようとする者は、これらの技能をすべて身につけていなければならないが、それ以外の優れた演奏家でも、読者の前に置かれたこの論考からさまざまなことを学ぶことができる。
菅沼のコメント:ここでチェルニーは、即興演奏に必要な能力として天性の素質、和声の知識、演奏技術を挙げています。確かにこれらは違う時代の即興の教本でも述べられているものであり、例えば16世紀、ルネサンス期だと和声の知識は当時の音楽理論の文脈に則して対位法の知識、という言葉に置き換わっていました。想像力(第一の分類に属するもの)があってもそれをアウトプットする技術がないと意味がない、という指摘ももっともです。ある種本能的な発想、理性的な知識、そして身体的な技術の三本柱を余すことなく提示することは、即興演奏のみならず演奏そのものに必要なもの、とも言い換えることができるかもしれません。
即興演奏は、さまざまな種類と段階に分類されうるものであり、学生が慣れ親しまねばならない順番で以下に記される。
第一:楽曲が始まる前のプレリュード(Vorspiele)
第二:楽曲の途中にある休止や主題への推移部、さらには協奏曲における終結部にあるカデンツァとフェルマータ
注:これら2種類は、[楽曲内で]部分的に必要であるにもかかわらず、ファンタジーの真の構成要素であり、事前に準備すべきものとして認識されるべきである。
第三:真の、独立したファンタジー(即興演奏)は以下の種類に細分化される:
- a. ひとつのテーマを、馴染みの作曲形式で演奏durchführenする
- b. 複数のテーマを一つの形に結び付け、演奏すること
- c. 真のポプリ、あるいは気に入ったモティーフを、どれか一つのみを展開させずに、移調やパッセージ、カデンツァなどで並べること
- d. あらゆる慣習的な形式による変奏曲
- e. 統一的なフーガのスタイルによるファンタジー
- f. 最も自由で制限のないタイプのカプリッチョ
もちろん、これら全ての分類は一つのファンタジー内で組み合わせて用いられうる。
菅沼のコメント:ここでまず、チェルニーは即興演奏を三つのタイプに分類していますが、第一と第二のものは「既存の楽曲に付随するもの/含まれるもの」であり、第三のものは「既存の楽曲とは関係のない、独立したもの」とさらにカテゴリー化することができるでしょう。
ここで重要だと私が考える点が二つあります。まずは、注で述べられている「事前に準備すべきもの」という文言です。即興演奏は完全な無から有を生み出すものではなく、これまでの音楽経験で蓄積されてきた自分の引き出しから自由に取り出し、組み合わせるものである、というイメージは研究や実践の場でかなり言われるようになり、定着してきていると思われますが、チェルニーのこの文言もそれを示すものになります。これは、即興演奏に馴染みのない現代の演奏家たちの希望にもなるでしょう。即興演奏のために何かネタを事前に準備することがむしろ奨励されているのですから、即興への取り組むハードルもかなり低く感じられるのではないでしょうか? 私も、演奏会などでは、そうした即興の「ネタ」を事前に準備する(=楽譜などに書いておく)こともしばしばあります。複数のネタを事前に準備しておいて、演奏しながらそれらを組み合わせていったり、瞬間的にどれかを選んだりしたりもします。こうしたことの蓄積により、事前準備なしの即興もより気楽にできるようになると考えています。
もう一つは、ポプリというジャンルです。これに関しては、また次回以降に特集する回をぜひ設けたいな、と考えています。ポプリというのは、「よく知られている旋律やその断片をつなぎ合せた曲(ブリタニカ国際大百科事典)」で、18〜19世紀によく作られた、そして即興されたジャンルです。まさに聴衆がよく知る馴染みのヒットチューンのメドレーであるポプリは、当時もかなり面白い楽曲が残されており、学ぶところの多いものになっています。現代版ポプリを演奏家が作ってみる、というのも、歴史的な即興演奏の実践として将来的な可能性が大いにあるものでしょう。ちなみに、チェルニーのポプリの説明での「どれか一つのみを展開させずに」というのは、例えば知られた旋律を三種類用いるとして、Aだけ重点的に使ってしまうとそれは分類上のaやdに近くなってしまうので、AもBもCも満遍なく使うものをポプリと説明していると考えられます。
この即興演奏の技術は、即興に対する生来の素質のように、勤勉さと学究により体系的に教育され、完成することができる。特に即興演奏は、確かな原則に基礎を置くことができるので、この教本の目的は、最も適している体系を順序立てで学び、迅速に上達してゆくことである。
菅沼のコメント:チェルニーは、即興演奏に必要な素質として先天的な才能を挙げていました。しかし、ここではそれだけではなく、後天的な学習の意義も強調されています。即興演奏は先天的な才能により全てが決定するものではなく、順序立てた学習と訓練により体得することができる。やはり、自分の「引き出し」を増やし、それを実践するための演奏能力を身に付ける作業は決して無駄ではないと言ってくれているようで、単に「教科書だからこう言わないと元も子もない(全て才能である、と言ったら教本の存在理由がない)」から以上の意味合いが込められていると、私は考えています。
これで、序文は終わりです。ここからいよいよ第一部が始まります。次回もどうぞお楽しみに。
- チェルニーに学ぶ!第19回 番外編~公開録音コンサートについて(2025/12/16)
- チェルニーに学ぶ!第18回 『第六章:ポプリについて』~紹介と簡単な分析(Op. 200⑬)(2025/12/16)
- チェルニーに学ぶ!第17回『第六章:ポプリについて』(Op. 200⑫)(2025/12/02)
- チェルニーに学ぶ!第16回 夏休み特別番外編②(研究紹介)(2025/11/04)
- チェルニーに学ぶ!第15回 夏休み特別番外編①(研究紹介)(2025/10/27)
- チェルニーに学ぶ!第14回『第五章:複数主題によるファンタジアについて』(Op. 200⑪)(2025/08/28)
- チェルニーに学ぶ!第13回『第四章:即興演奏について③』(Op. 200⑩)(2025/08/11)
- チェルニーに学ぶ!第12回『第四章:即興演奏について②』(Op. 200⑨)(2025/07/03)
- チェルニーに学ぶ!第11回『第四章:即興演奏について①』(Op. 200⑧)(2025/07/03)
- チェルニーに学ぶ!第10回『カデンツァについて』(Op. 200⑦)(2025/06/13)
- チェルニーに学ぶ!第9回『TPOに合った、即興的な「前奏曲」』(Op. 200⑥)(2025/05/15)
- チェルニーに学ぶ!第8回『半音階と異名同音と即興の心構え』(Op. 200⑤)(2025/04/24)
- チェルニーに学ぶ!第7回『即興の例とエチュードの役割』(Op. 200④)(2025/02/10)
- チェルニーに学ぶ!第6回『前奏曲の役割と「技」』(Op. 200③)(2025/01/09)
- チェルニーに学ぶ!第5回『即興に必要な学びとは?』(Op. 200②)(2024/12/26)
- チェルニーに学ぶ!第4回『即興の定義』《ファンタジーへの手引き》Op. 200①(2024/12/26)
- チェルニーに学ぶ!第3回『即興演奏の伝統』~ファンタジア小史②(2024/11/14)
- チェルニーに学ぶ!第2回『ファンタジアとは?』~ファンタジア小史①(2024/08/29)
- チェルニーに学ぶ!第1回『はじめに』~筆者自己紹介&西洋における即興(2024/07/25)