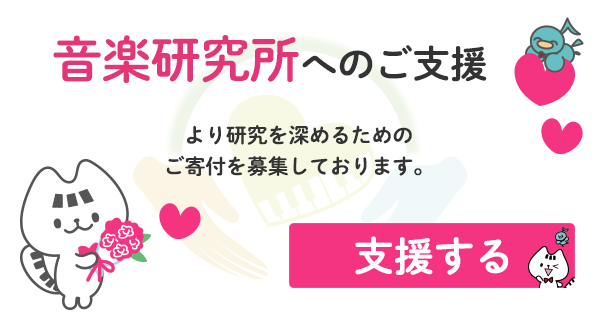チェルニーに学ぶ!第1回『はじめに』~筆者自己紹介&西洋における即興
~創造の楽しさを日々の練習に~
みなさま、はじめまして。2024年度より協力研究員としてピティナにお世話になっております菅沼起一と申します。
この度、私の研究をご紹介するコラムを連載させていただくことになりました。連載の第一回として、まず、私の専門分野や、これまでに行ってきた研究、これから行う研究について簡単に自己紹介をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
私は、リコーダー奏者として音楽のキャリアをスタートさせましたが、リコーダーの専攻学生時代から現在に至るまで、もっとも熱心に取り組んできた分野が「ディミニューション」と呼ばれる即興演奏技法です。これは、主に16〜17世紀にかけてヨーロッパで多くの手引書が出版され最盛期を迎えた演奏習慣で、既存の書かれた(作曲された)旋律を、演奏時により小さな音符に「分割」して即興的に装飾していくものです。
まずは、私が16世紀後半に出版されたディミニューションの教科書の譜例を演奏した動画があるので、ご覧いただきます。
ジローラモ・ダッラ・カーザ『ディミニューションの真の方法』(ヴェネツィア、1584年)より、作者不詳の《ばらの花》。動画の前半は装飾のない原曲のヴァージョンを演奏し、後半はダッラ・カーザによるディミニューションが付けられたヴァージョンを続けて演奏しております。

《ばらの花》比較楽譜。一段目がダッラ・カーザによるディミニューションで、原曲(二段目から下の6パートが原曲の楽譜です)のカント声部に夥しい装飾を施しています。
このディミニューションについてもっと知りたい、深掘りしたい、と思い、私は修士課程より音楽学専攻の門を叩き、研究と演奏の両輪でこの分野に取り組んできました。昨年、ドイツのフライブルク音楽大学に提出した博士論文でもディミニューションについて取り上げましたが、その内容は、16世紀にディミニューションの技術が極まった結果、それまでの最小音符だった16分音符がさも陸上競技の世界記録のように更新され、32分音符という新しい音符が誕生した、その経緯についてです。演奏家たちがディミニューションを通して実現しようとした「速弾きの美学」は、楽譜で用いられる音符をも変化させていきました。ディミニューションは、現代の我々から見ても血湧き肉躍る、ワクワクするようなヴィルトゥオーゾな世界なのです。
ところで、このように私の専門にしていた16~17世紀は即興演奏が今よりもっと身近な世界でした。当時の音楽の世界を、専門家たちは海に浮かぶ氷山にたとえて説明します。いわく、「当時の音楽のうち、現代の我々に伝わっている(=楽譜という形で後代に残されている)部分は氷山の一角、海から顔を覗かせている部分でしかない。氷山の大部分は海面の下に沈んでいて見えないように、当時の音楽の多くは即興的に演奏され、そして記録されないまま消えていった」と。しかし、そのような即興演奏も、先述の手引書などによりどのような実践が行われていたか、その一旦を知ることができます。私の研究は、そうした「氷山の見えない部分」に(どうにかして)光を当てていくものと言えるでしょう。
現在のピアノ演奏で取り上げられる作曲家の多く——J. S. バッハ、モーツァルトやベートーヴェン——も即興演奏の名手だったというのは有名な話です。実は、遠く中世にまで遡る鍵盤楽器による即興演奏には絶えざる長い伝統があります。オルガンやチェンバロといったピアノの先達たちによる即興演奏の記録は15世紀から一貫して見つかり、そしてそれはピアノ演奏全盛の19世紀にも脈々と受け継がれていきました。たとえば、練習曲でお馴染みのカール・チェルニーは、即興演奏に関する教科書や記述を数多く残しています。その代表的なものが私の研究の主たる対象である『体系的なファンタジーの手引き(即興演奏教程 第1巻)Op. 200』(1829年頃?)です。ドイツ語で書かれた本書の英訳を手がけたMitchellは、チェルニーの作品200を皮切りに、即興演奏に関する話題が彼の「キリ番」の作品番号(200, 300, 400...など)で繰り返し登場することなどに言及しつつ、チェルニーの教育活動における即興演奏教授の重要性が現代のピアノ教育において低い評価のままであることに対し問題を提起しています。チェルニーは練習曲のイメージが強い人物ですが、彼の即興演奏の教科書は当時のピアノのヴィルトゥオーゾたちがどのような即興演奏を行っていたか(=楽譜に書かれた曲を弾く以外にどのようなクリエイティヴな演奏活動を行っていたか)を知ることが出来る重要な資料であり、現代の我々の演奏の幅を広げる、より豊かな演奏実践を行っていくために有益な情報を数多く提供してくれます。
こうした過去の即興演奏は、チェルニーの例のように演奏の引き出しを増やすためのメソッドがしっかり提供されていることが多く、実は現代の我々にとっても敷居の高い実践ではありません。そして、こうした引き出しを増やすためのメソッドは、実は当時の音楽の様式感を身につけるのにもとても役に立つのです。何より、即興演奏は本番で上手くいくと自分が当時の名演奏家/作曲家に一歩近づいたような気がしてワクワクします! そうした即興演奏の歴史を振り返り、現代のピアノ演奏実践・教育にどう活かしていけるのか。これが私のピティナでのプロジェクトです。
それでは、次回はチェルニーに至る鍵盤楽器の即興演奏、その系譜を概観してゆきます。どうぞよろしくお願いいたします。
- チェルニーに学ぶ!第19回 番外編~公開録音コンサートについて(2025/12/16)
- チェルニーに学ぶ!第18回 『第六章:ポプリについて』~紹介と簡単な分析(Op. 200⑬)(2025/12/16)
- チェルニーに学ぶ!第17回『第六章:ポプリについて』(Op. 200⑫)(2025/12/02)
- チェルニーに学ぶ!第16回 夏休み特別番外編②(研究紹介)(2025/11/04)
- チェルニーに学ぶ!第15回 夏休み特別番外編①(研究紹介)(2025/10/27)
- チェルニーに学ぶ!第14回『第五章:複数主題によるファンタジアについて』(Op. 200⑪)(2025/08/28)
- チェルニーに学ぶ!第13回『第四章:即興演奏について③』(Op. 200⑩)(2025/08/11)
- チェルニーに学ぶ!第12回『第四章:即興演奏について②』(Op. 200⑨)(2025/07/03)
- チェルニーに学ぶ!第11回『第四章:即興演奏について①』(Op. 200⑧)(2025/07/03)
- チェルニーに学ぶ!第10回『カデンツァについて』(Op. 200⑦)(2025/06/13)
- チェルニーに学ぶ!第9回『TPOに合った、即興的な「前奏曲」』(Op. 200⑥)(2025/05/15)
- チェルニーに学ぶ!第8回『半音階と異名同音と即興の心構え』(Op. 200⑤)(2025/04/24)
- チェルニーに学ぶ!第7回『即興の例とエチュードの役割』(Op. 200④)(2025/02/10)
- チェルニーに学ぶ!第6回『前奏曲の役割と「技」』(Op. 200③)(2025/01/09)
- チェルニーに学ぶ!第5回『即興に必要な学びとは?』(Op. 200②)(2024/12/26)
- チェルニーに学ぶ!第4回『即興の定義』《ファンタジーへの手引き》Op. 200①(2024/12/26)
- チェルニーに学ぶ!第3回『即興演奏の伝統』~ファンタジア小史②(2024/11/14)
- チェルニーに学ぶ!第2回『ファンタジアとは?』~ファンタジア小史①(2024/08/29)
- チェルニーに学ぶ!第1回『はじめに』~筆者自己紹介&西洋における即興(2024/07/25)